正直な話、私の手には負えなかったのです。
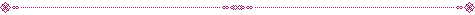
愚かな私は、二人を残して出て行ったときにはそう、あれをぶちのめして馬鹿なことはやめろと全部壊して、あの方のお願いも叶えられて一石二鳥、とかしか考えていなかったんです。
出来ると思っていたんです。高慢にも。
だって私だって成長したんです。
努力したんです。
出来なかったことが出来るようになって、見える世界が広がったんです。
──ああ、浅はかにも程がある。
私が成長したからと言ってあの人の元に追いつけるわけではなかったのです。
私が成長するのと同じように、あの人も努力して、成長して、さらに世界を広げていたんです。
あの人が見ていた世界が私には見えなかった。ひと欠片たりとも。
私とは次元が違ったのです。
――私はあの人には敵わない。
私がそれに気づいたとき、身体は無様にあの人の足元に転がっていました。
──私はあの人の足元にも未だ及ばない。
私がそれに気づいたとき、おろかにも私は数年の年月を無為にしていました。
そしてそれ以上を私が理解することは出来ませんでした。
あの人が私の理解をはるかに超えていたから。
もちろん、自分に対する落胆が、それ以上考えることを避けていたのもあるのでしょう。
圧倒的に準備が足りなかった。そう私は痛烈に感じました。
力が及ばないなら及ばないなりに、対策を講じて絡め取るくらいの……それが出来なくとも、足止め、いや、目くらましになる程度の工夫をしてしかるべきだったのに、私はまさにこの身体ひとつであの人の前に立ちふさがってしまったのです。
あの人は立ちふさがった私を見て、眉一つ動かすことなく、そう、あたかも飼っている黒猫がじゃれついてきたのを傷つけないように引き剥がす、そんな自然さで私を──────ああ、思い出すだけでも腹立たしい。
何が腹立たしいといえば、明確な敵意を持って対峙している私を愛玩動物と同列にしか扱わないあの人も、そしてあの人に傷ひとつつけることが出来ない私の爪も。何もかもが忌々しい。
そして何の対策も講じず飛び込んだ私は、あの人の籠から出られなくなってしまっていたのです。
気づいたのは少し経ってからでした。本当に私は愚かでした。
最初は自由意志でそこにいたんです。いたつもりでした。自分の意志でここにいるんだと、隙を窺っていつかぶちのめしてやると、そう思っていたのです。
でもしばらく時が経って、さすがに私も冷静になりました。今のままではとてもじゃないけれど害意をもって触れることすら出来ない。そう気付いたのです。
戻って今度はちゃんとみんなで計画を立てて壊そう。
そう思えるようになった段でようやく気がつきました。出られないことに。
とても焦りました。
ここから出せと抵抗してみようかとも考えましたが、明らかに無駄、むしろ後々の障壁にしかならない結末に終わりそうでした。
むしろ出て行こうという意志を悟られるだけでも、ここを守る防壁が厚くなって脱出が困難になるに決まっています。
自力で悟られることなく、ここから脱出しなければならない。
とても焦りました。
何故ならここはあの人のテリトリー、この領域内で起こするべての事象はあの人の手中なのですから。
そして私はそこに囚われている。
家主に存在を認識されていないネズミであれば、きっとうまく立ち回って情報収集することが出来たのでしょう。
しかし私は残念なことに、家主に飼われる黒猫の一匹でした。
存在を認識され、ほぼ常時監視下にある私がこそこそと嗅ぎまわり、この領域の情報を得るのは困難を極め、それなりに長い月日と苦痛が代償でした。
そう、それでも私は見つけたのです。かすかに差し込む一筋の光を。
この光に気づかれる前に。
私はがむしゃらにその光に手を伸ばしました。
手を伸ばしてから、脳を焼く酷い痛みに、あの人がそんな穴に気づいていないはずがないということを深く認識させられました。
光が差しているからといって、穴が外と通じているとは限らないと言うことなのでしょう。
──もしかしたら、嵌められたのかもしれない。背筋に冷たいものが走りました。
しかし、ここで外界を感じ取れる場所はここしかありませんでしたし、たとえ罠であったとしてもここがもっとも外界と近い、そして唯一の場所であることには間違いありません。なので、これが私にとっては恐らく最大で最後のチャンスであろうと、びりびりと激痛を訴える四肢を何とか前に繰り出してとにかく光の差すほうに向かってもがきました。
──痛い。
──苦しい。
────前に進まなくては。
────今はとにかくそれだけを考えなくては。
──────ひどく焼かれて身体の感覚がない。
──────ああ、私は私として動いているのか。
──────この身体を動かしているのは何者なのか。
──────この身体、とはどこにあるものだろうか。
────────どこからどこまでが私なのか。
────────光はもうすぐそこに。
完全に無我夢中でした。
ふと我に返ると、いつの間にか、私はどうやら外にいるようでした。
外、と言ってもここがどこなのかも今の私にはわかりませんでしたが。
そして外に出て私が何をすべきなのかも今の私にはわかりませんでしたが。
命からがら脱出してきた今の私は何も持っていないのです。
すべてをなくしてしまった、漠然とそう思いました。
失ってしまったものの記憶を失ってしまった私は、その場から動くことができませんでした。
肌を撫でる初夏の風の温度も、明けてくる夜の空気のしっとりとした重さも、細波のように風に揺れる葉のそよぎも、虫や鳥の声も。何ひとつ、今の私は享受することは出来ませんでした。
何の音もしない、香りもしない、暖かさも感じない、私が何かに焼ききられて破られて塗りつぶされて私でなくなる感覚しか感じ取ることが出来ませんでした。
外に出られた、という安心感からかぼんやりと薄れ行く意識の中で、誰に聞かせるでもなく、私は呟いていました。
「ごめん、失敗しました」
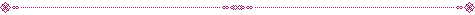
そうして、少女は暗い夜明け前の森の中に眠っていたのだった。
